2020年のオリンピックは東京に
めでたく決まったことは周知の通りですが、
気になったのは
その五輪招致の状況を見ていて思ったこと…
内容は、IOCの調査報告書では、
東京は「安全面」と「財政面」で安定していることから、
東京は高い評価を受けている、といったものですが、
このことから言い換えれば、
東京・イスタンブール・マドリードとも
決め手に欠けていた、
と言えるのではないでしょうか?
つまり大体、勝負事や交渉事の8割位は、
事前に勝負の結果が決まっていると
言えると思います。
例えば2016年のオリンピックの
開催地はリオデジャネイロですが、
南米地域では初の五輪開催です。
この「初開催」というものは
メンタル面において強く影響するので、
東京のように過去に開催暦がある国には、
招致において絶対に有利になれない要素があります。
それだけに、
他の候補地は最初から超えられないハンデを
背負っているので苦しい戦いを強いられるわけですが、
逆にリオデジャネイロは有利に招致合戦を進められるわけです。
このようにメンタル面が影響してしまう勝負事や交渉事は
事前の段階で勝敗が見えていることが多いと思いますが、
私自身の営業経験からしてもそのことがありましたから、
勝負前の状況を冷静に観察することは非常に
大事であると言えると思います。
例えば、歴史上の史実でいうと、ナポレオンが戦った
1805年のアウステルリッツ三帝会戦がいい例だと言えます。
(フランス・オーストリア・ロシアの三皇帝が
アウステルリッツの地に一堂に集結したといわれる珍しい戦い。)

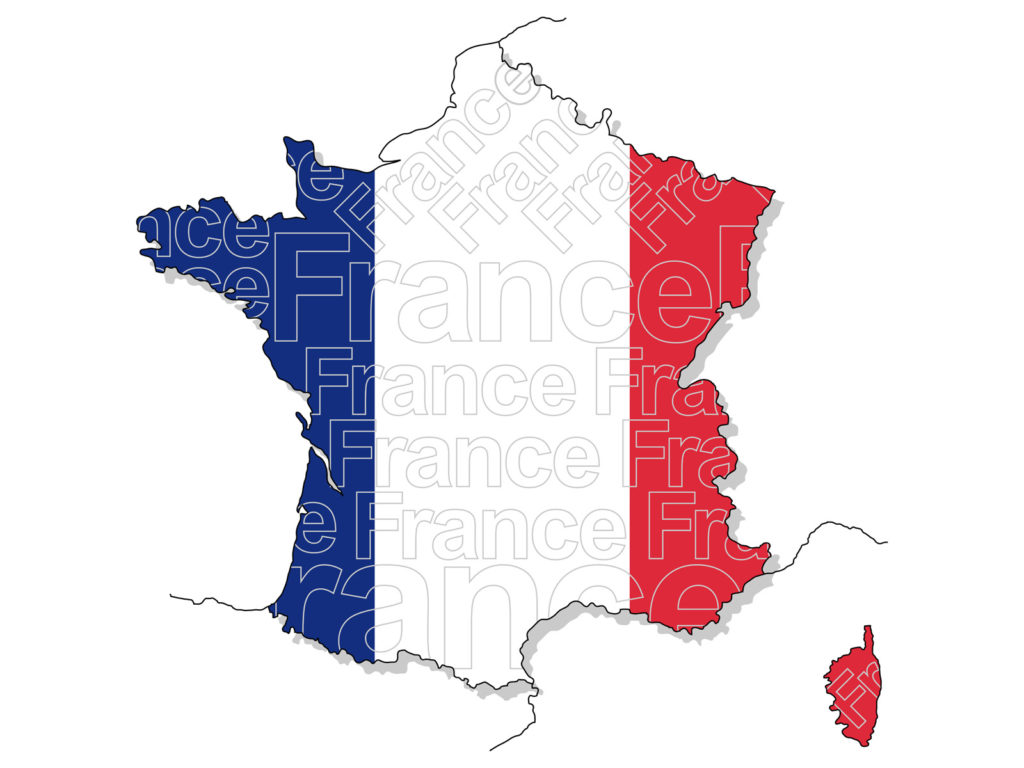
世にも珍しいアウスルリッツ三帝会戦
この時のナポレオンが率いる
フランス軍は兵力の上では劣勢でしたが、
ナポレオンが相手の行動を上手く読み取って、
相手の隙をついて攻撃することで、
相手国の兵士の動揺を誘い出して、
結果としてフランスが劇的な勝利を収めた戦いです。
勝って当たり前の状況でも、
最前線がメンタル面において負けてしまえば、
勝負にはならないのです。
さらに数では勝っていても、
負けるためのレールに乗ってしまっては
勝てる勝負でも勝てないことが
自明の理だとよく解ります。
このことを 、
「戦争論」を書いたドイツ(プロイセン)の
有名な軍事学者であるクラウゼヴィッツは
「戦争芸術の粋」と表現しましたが、
まさか!と言える勝利と、
見事に勝負を決めるレールを敷き終えた
ナポレオンに対する驚きを表していると言えます。
ちなみにそのナポレオンですら、
後のロシア遠征では予想外の消耗戦を強いられて
大敗北を喫してしまっています。
後退しまくるロシア軍の行動を
想定出来なかったのが敗因ですが、
ロシア軍からすれば広大な領地を
生かした戦略として当然の選択だったのかもしれません。
つまり、
ナポレオンが予測できなかったことを
ロシア軍が行動できたから、ロシア軍が勝利したのではないか、
ということも言えるわけです。
これぞまさに、孫子の兵法にある
「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」ですね!
